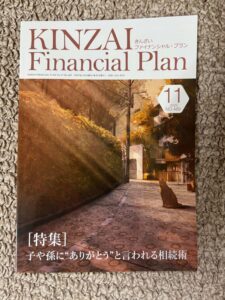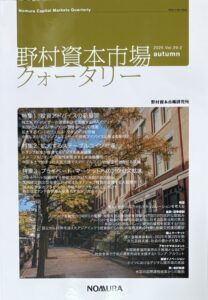私の心情(307)―取り崩しインタビュー第11弾:会社の福利厚生制度が資産形成の力に
 東海道を歩きつなぐ
東海道を歩きつなぐ
64歳のFさんは都内にお住まいで栃木県の企業に勤めていらっしゃいます。56歳の奥様と83歳のお母さまと同居をされていますが、お子様はいらっしゃいません。
現在、週2回程度、新幹線通勤による出社が必要なのですが、それ以外は自宅からのオンライン業務で対応できるようになっています。あと1年で定年を迎えることになりますが、「会社が必要だといってくれるのならもう少し働いてもいいとは思っているのですが・・・」と話され、再雇用への強いこだわりはないようです。
定年まであと少しとなり、最近はかなり積み残している有休を月に3日程度取りながら、のんびりとした生活を送っています。現在、その有給を使って東海道を歩き通すプランを実行していて、休みのたびに前回の最終駅から再開して、今は日本橋から小田原まで歩き終えたところだそうです。
来年から収入は半減
年収は現在900万円強で、契約社員として働いている奥様の年収と合わせて1100万円くらいになります。一方、支出は900万円くらいと多いのですが、現状の収支で見ると、毎年200万円くらい資産が増えるペースです。
しかし退職後、公的年金に頼る生活となると、Fさんの年間収入は一気に300~400万円と大幅に減ります。奥様がまだ4年ほど働いてこれまで通り200万円の年収があるとしても、来年以降の年収は500~600万円に低下します。資産収入への依存が一気に高まることになります。
外貨建て個人年金で当面はカバー
支出の削減は必須ですが、Fさんの見積もりでは、65歳になった段階で、無駄な消費を削減すれば年間支出は800万円くらいに、さらに生命保険の掛け金が終わると700万円くらいには減らせるはずとみています。
それでも、まだ十分ではなく、収支の差額は100‐200万円が見込まれ、これを資産収入でカバーすることになります。現在保有している外貨建て年金保険が65歳から10年間、毎月500ドル受け取れるので、1ドル=145円で換算すると年間80‐90万円の資産収入となります。これにあと運用資産の取り崩しで残りをカバーするように考えるとしています。
なお持ち家に住んでいることで、家賃の心配はないし、住宅ローンもありませんので、住宅関係では差し当たって生活を圧迫する要因はありません。
長期で見ると
ところでFさんは、「自身のライフプランは90歳までを想定している」と考えています。公的年金以外に65歳から75歳までは外貨建て年金で合計800万円受け取れるとしても、その先は本当に足りない部分を運用資産からの資産収入として作り出す必要があります。これは決して簡単ではありません。
財形貯蓄を全額おろして資産運用に
それをカバーするための資産を伺いました。
資産運用へ本格的に動き始めたのは、金利の低さに気が付いて財形貯蓄の1300万円全額を引き出してその一部を運用に回すことにした十数年前です。NISA口座では、オンラインの一任勘定、そのほかでは外貨預金、株式などを対象にしたことで、現在その資産が1900万円ほどになっています。
その内訳は、預金が900万円くらいです。NISAではつみたて投資枠を目いっぱい使って、放ったらかしができるオンライン一任勘定に資金を預け、現在400万円に。外貨預金は300万円、株式は財形貯蓄の資金で買い増す以前から3銘柄ほどありましたが、現在9銘柄300万円。株式は少しずつ増やしていますが、それは1月から12月まで毎月何らかの株主優待が受け取れるよう銘柄を選んでいるところだそうです。まだ完成はしていないとのことですが、これも楽しみの一つになっています。
その他に自社の持ち株が1000万円ほど、合計で2900万円ほどの金融資産を保有しています。
多めの退職金にも期待
まだ手元にない資産として、退職金と退職時点で引き出す予定の確定拠出年金があります。前者は2000万円程度、後者は300万円とのこと。40年に達する勤続年数から想定すると、両方を一度に引き出しても退職所得控除がフルに効いてくるため、税金は極めて少ない負担で済みそうです。そのため、2300万円をそのまま資産に組み込むと、金融資産総額は5200万円、うち預金は62%の3200万円となりますから、かなり余裕が出てくることになります。
なお、Fさんは退職金からも投資を考えているとのことです。ビットコインとか金の積み立て投資といったアイデアが出てきました。また、以前大損をしたことがあったFXや、後の処理が大変になると聞いた別荘などの実物資産は、どちらも手を出すつもりはないようです。
その資産を生活費に充当するために取り崩す場合の順序を伺ったところ、「預金→外貨建て資産→株式など」と考えているそうです。ただ、900万円の預金と退職金や確定拠出年金の受け取りで、退職時点に3200万円ほどの預金が出来上がりますが、200万円の収支不足をカバーするとこれでも16年分にすぎません。少し想定する資産収入額が高いように映ります。
住宅資産は1億円
一方、住宅は持ち家で築13年になりますが、9年ほど前に亡くなった父親の遺産1500万円のうち半分ほどを使って、住宅ローンを完済しています。家賃、ローン負担がなかったことは大きなメリットですが、自宅の資産価値が1億円程度に高まっているのもプラスといえます。
将来、資産が不足した折には、「この自宅を担保にリバースモーゲージを考えてもいいのではないか」とも値踏みしています。
インタビューを終えて
やはり大手企業に勤務してきた人は、資産形成にいろいろな面で有利だと改めて思います。給与水準の高さもさることながら、確定拠出年金制度の充実、自社株持株会の存在、そして何より退職金の多さです。私は16年以上務めた会社が倒産したこともあって、自社株の持株会には一定以上の警戒感がありますし、退職金にも若いうちは期待すべきではないと思いますが、それでも結果として大きな資産を残すことができた人にとっては、いい制度であったといえます。これは確定拠出年金でも同じことでしょう。
資産形成で有利だったということは、退職後の資産活用でも力になります。ただ、退職後の資産運用を現役時代の延長のように単純に考えるのは危険な可能性もあります。退職金で、ビットコインなどへの投資は、かなりハイリスク・ハイリターンなものですし、自宅を担保にしたリバースモーゲージもまだまだ普及しきれていない点で、思わぬ落とし穴があるかもしれません。
やはり、リスクを高めにとる投資は現役時代だけにして、退職したらより保守的な資産運用に転換するのも考えてみるべきではないでしょうか。